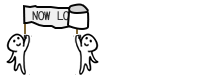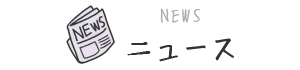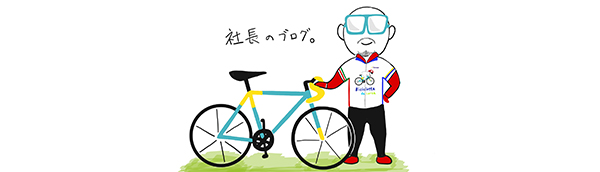蒲生のサムライ会社と浦和興産
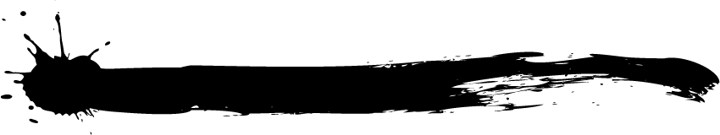
![]()
![]()
Googleで、『蒲生 サムライ会社』
と検索すると、
なんと!
私たち浦和興産のホームページ>ニュース>浦和便り>サムライ会社が2番目か3番目に出てきます。
これだけの実績⁈があるのだからと、思い切って『蒲生のサムライ会社』である『蒲生殖産興業株式会社』へ表敬訪問しました。
時代がかった立派な長屋門のある『街道をゆく 肥薩の道』に紹介された『サムライ会社』へ入ってみました。
TVで見たとおりの趣きと雰囲気に圧倒されましたが・・
人の気配がありません。
あれ、お休みなのか?
(この日は、とび石連休の谷間の月曜日でした)
と思いましたが・・。
「蒲生衆のいうことなら聞いてやれ」
という同情が明治の廃藩置県という士族の瓦解の際に、藩幹部にあったに違いないと、司馬遼太郎さんは『肥薩の道』で述べています。
(私はこのあたりの司馬遼太郎さんの歴史へのまなざし・・寛容さ、やさしさをとても好ましく私は思うのです)
蒲生衆は関ヶ原でも戊辰戦争でも損な役まわりを引き受けてきたことへの藩幹部の感謝の念や貧乏であることへの同情から、
この時代、薩摩藩はもとより全国的にも皆無である士族の経済的な保証としての藩有地(山林)の払い下げが行われ、
『蒲生士族共有社』が奇跡的にも誕生します。
この士族共有社の事業の第一の目的として、
『蒲生衆の子弟の東京遊学の学資』(奨学金制度)
が生まれ、今日まで続いているそうです。
そんな“サムライ魂の詰まった歴史を持つ会社“がこれからも続いて欲しいと願い、
表敬訪問のリスペクトする気持ちだけ置いてきました。


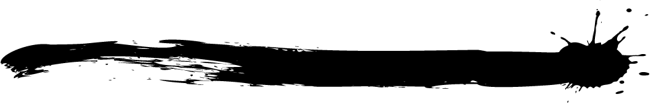
![]()
![]()
蒲生の「サムライ会社」はとても興味深いです。
明治の時代に生まれた会社が現代でも続いているとはなかなか無いことですね。
サムライ会社の役割として土地に植林や牧畜をしそこで採れた物を平等に社員に配分したり、
利益は子供たちを東京の学校へ行くための資金にしたりととても有益なことに使えていることがなによりも素晴らしいと思います。
明治の初頭からに上級教育が受けられるようなシステムが鹿児島の地にあったことも驚きです。
現在でも林業を営み育英会を運営して子供たちのために奨学資金を提供しているそうです。
サムライ会社についてもっと知りたいと思いました。
![]()